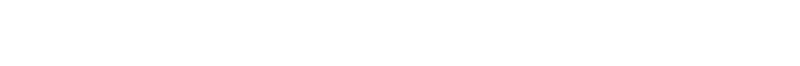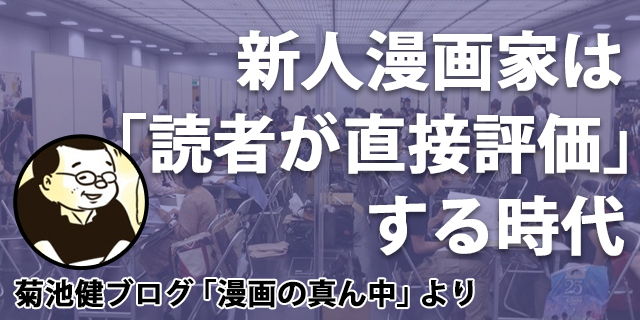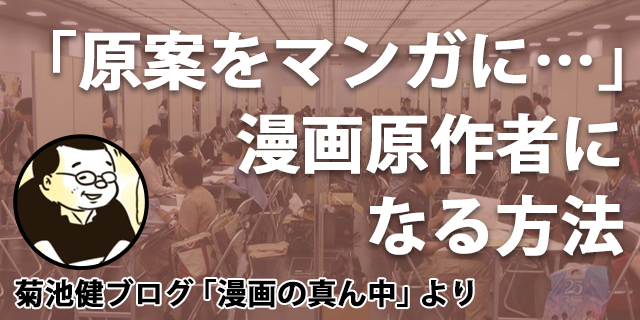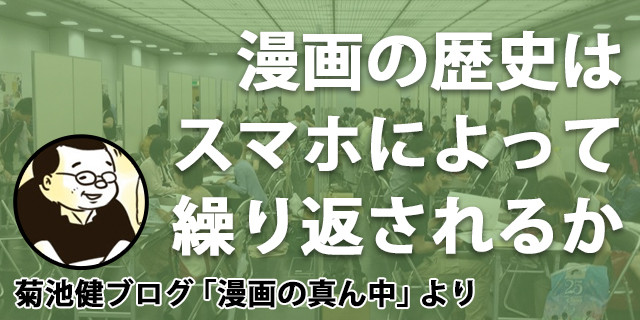集英社『ジャンプSQ.』矢作康介編集長インタビュー(1)

人気マンガ雑誌の編集長さんに、これまで関わってきた作品や編集者の仕事、新人作家について考えていることなどをお伺いする企画「編集長の部屋」より、『ジャンプSQ. 』編集長・矢作康介さんへのインタビュー第1回(全3回)を特別掲載!
自分たちからメディア化を働きかけることは少ないです。
むしろ、良い作品を作り、良い形で映像化してくれるオファーがあって、初めて映像化するという形です。

▲集英社『ジャンプSQ. 』(以降SQ.)編集長・矢作康介さん
―― 矢作さんご自身のことを聞かせてください。
入社が94年で、当時はマンガが売れに売れていた『週刊少年ジャンプ』(以下、ジャンプ)全盛期でした。
入社年の夏の合併号は647万部、年末の合併号は653万部という最大部数を更新し続けていた時期。
でも、実状は『幽☆遊☆白書』も終わり、『ドラゴンボール』も『SLAM DUNK』も近い将来最終回を迎えることが見えていて、このままではいずれ大変なことになるという感じ。
編集部内でも「もう、部数を表紙で大きく謳うのはやめよう」みたいな雰囲気でした。
当時、現在はコミックゼノンを発刊している㈱コアミックスの堀江信彦社長がジャンプの編集長でした。
就職活動の時に、堀江さんが大学に講演に来てくださった。
この時の話が本当に面白くて集英社を受験。
希望して配属された先が堀江編集長の週刊少年ジャンプ編集部でした。
最初のうち仕事は『DRAGON QUESTダイの大冒険』『キャプテン翼 ワールドユース編』など、先輩の担当作品を引き継ぎました。
いくつかの作品を経験して、4年目の97年に、『トリコ』の島袋光年さんが描いた『世紀末リーダー伝 たけし!』を立ち上げました。
島袋さんは沖縄から出てきて持ち込みをしてきたときからの付き合いでした。
この新連載は『ONE PIECE』が始まる一つ前の号からの連載で、初回は読者アンケート1位でした。
その次の『ONE PIECE』も初登場で1位を取って、ジャンプに新しい力が出て来たなと実感し始めた頃でした。
翌98年、『HUNTER×HUNTER』の連載立ち上げを担当しました。冨樫先生は『レベルE』から担当していました。
翌99年に当時新人の岸本斉史さんと『NARUTO -ナルト-』を立ち上げました。『NARUTO -ナルト-』は、副編集長になるまでの9年間担当しました。
―― いやぁ、改めてうかがうと凄いですね!
たまたまこのタイミングで素晴らしい新人作家が集まってくれたということに尽きます。
冨樫先生はとにかく何を描いても面白いので、編集者としては出来ることは少なかったです。
というより、マンガについて何も分らない素人がいろいろ学ばせていただきました。
それでも作品中で「ここが分かりにくいです」などと指摘をすると、かならず分かりやすく、より面白く直してくださいました。
『レベルE』のタイトルは、「地球にはいろんなエイリアンがすでに入り込んでるんです。
この世界はそういう段階(レベル)なんです」という設定を意図して、先生がつけられました。
なので、オムニバスを予定していて主人公の王子も序盤の3話目くらいまでのキャラだったんです。
その後は、全く違うエイリアンをシリーズ毎に見せるはずでしたし、怖いだけの話を描いたりもする予定でした。
最初は編集部も、先生がお描きになりたいもので、という感じでした。
ところが、1話目のアンケートが素晴らしく、周囲の雰囲気がガラリと変わりました(笑)。
結果的に編集部のお願いを先生に聞き入れていただき、王子を登場させながら連載が続きました。
そしてその後、満を持して『HUNTER×HUNTER』の連載を開始しました。
私は『HUNTER×HUNTER』のハンター試験終盤の頃に、冨樫先生の担当を降りて『NARUTO-ナルト-』に集中しました。
『NARUTO-ナルト-』を丸9年担当したのち、副編集長になり漫画の担当から外れました。
週刊少年ジャンプ編集部は当時、副編集長が3人いまして、予算管理や雑誌の台帳作り、アニメ化などのメディア担当などをします。
アニメ制作の製作委員会などに出席して、編集部の意思を作品作りや宣伝・広告に反映させます。
最終的に週刊少年ジャンプには18年間在籍し、2012年にジャンプスクエア(以降SQ.)の編集長になりました。
―― まさに最前線の連続ですねぇ! その編集長への異動はどういうきっかけだったんですか?
特別大きな理由はなかったのですが、年次などで回ってきたのでは(笑)。
元々、SQ.は茨木政彦が週刊少年ジャンプの編集長時代に立ち上げた雑誌。
週刊との人材交流もかなり行われています。
―― メディア化に強い矢作さんがSQ.に異動して、メディア化を強化する人事かなとも思いましたが。
私自身には特別そういう所はありませんし、自分たちからメディア化を働きかけることは少ないです。
むしろ、良い作品を作り、良い形で映像化してくれるオファーがあって、初めて映像化するという形です。
最近も『終わりのセラフ』のアニメ化が決定しましたが、これも素晴らしい制作スタジオなどが加わった、凄い座組みです。
やはり、力のあるスタジオに制作してもらわないと、話題にもならないですし、監督も若くてセンスのある方にして欲しいですし、そういうところはこだわりたいです。
そういったオファーが来るようにするために、しっかりとマンガを作るということを地道にやっていこうと考えています。
―― 印象に残った作家となると、やはり岸本先生でしょうか。
岸本先生は、初対面はほっそりとしていて優しい人柄で、
アクションマンガを描くようなタイプには見えなかったのですが、アクションに関する構成やセンスがとにかく素晴らしかった。
個人的には、アクションを描ける人は運動神経が良くて、体で描いているところがあると思います。
映画やアニメからの学びもあろうかと思いますが、岸本先生も運動神経が良いのだと感じます。
あとは「とにかく人の話を良く聞く」作家だと思います。
編集者は、作家が必死で作ってきたものを、時にいろいろな形で否定しないといけないわけですが、岸本先生はその時々で編集者の話をがっちり受け止め、じゃあどうすれば良いのかを前向きに考えることが出来る作家さんです。
作家さんには十人十色、いろんなスタイルがあると思いますが、人の意見を冷静に聞いて客観的に作品作りに活かすという事はかなり難しい。
良い仕事をし続けられる、作家としての才能の一つだと思います。
私以降の担当編集者たちも、岸本先生と仕事をしているとこの作品を一生懸命頑張ろうという気持ちが湧いてくる、と言っていました。
これはいい影響を与えあえる関係でしょう。
―― 「良く聞く」というと、例えばどんなエピソードがありましたか。
「良く聞く」というのとはちょっと違う話ですが、岸本先生との話で記憶に残っているエピソードがあります。
マンガ作りではしばしば、作中のシーンやセリフを読者に強く印象付けておく必要があります。
物語の終盤などで回収して読者の心を動かす、キーになるシーンやセリフ、いわゆる「前フリ」ですね。
ある時期、週刊連載19ページの中で、その「前フリ」を数週間に渡って何度か入れることで、なかなか話が進まない事がありました。
私はしびれを切らして、ある週の打合せで「今週はこれを入れずに、もっと話を進めた方が良いのでは?」と指摘しました。
その際、岸本先生はしっかり話を聞きつつ、「確かに、話を先に進めるのも大事です。でも、読者は普段の生活の中で、例えば食事をしたりしながら、僕らが思っているよりかなり適当にマンガを読んでいたりする。
僕はどうしても読者に覚えておいて欲しい所は、自分が読者に伝えた、と考える3倍以上は描いておかないと心配なんです。」と言われました。
読者によってマンガがどう読まれるか、ということに深く心を砕いている姿に感銘を受けました。
―― 一昨年に、AnimeExpoという、アメリカ最大の日本のコンテンツのフェアに行ってきたのですが、
とにかく『NARUTO-ナルト-』のコスプレーヤーが沢山いて印象に残っています。
岸本先生は海外への展開も意識していたのでしょうか。
それは最初から意識していたのかもしれません。
まず、忍者ですね。それからあの金髪で瞳が青いビジュアルです。
当時、「金髪で青い瞳は読者から遠い。共感しづらい。これはウケないんじゃないの?」と指摘したんですが「いや、これが海外でウケるんですよ。」と、話されていました。
連載が続くかどうかも分からない時期ですから、あくまで冗談っぽくですが(笑)。
ライバルキャラに純和風のキャラを用意したり、里の情景にスチームパンクっぽさがあったり・・・。
それをマンガに取り入れたことは、本当に才能だと思います。
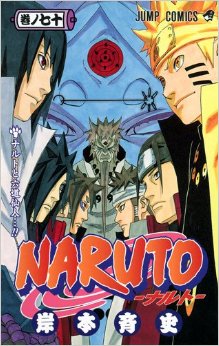
▲最近、完結された『NARUTO―ナルト』シリーズ。
編集者は作品をずっと出し続けることを請け負わないといけないと思います。
―― 矢作さんにとって、マンガ編集者とは、どんな仕事ですか。
先輩には「黒子だ」と教わったこともありますが、私は、キャッチャーの仕事と似ていると思います。
ピッチャーたる作家は、自分の決め球を自信満々に投げ込んでくるわけですが、その都度、弱点も指摘しますし、投球の組み立てを一緒に考えたりもする。
ピッチャーの調子の悪いときは、ミットの綿を抜いて良い音をさせたりみたいに、自信を持たせることも考える。
バッターたる読者を分析しながら、ピッチャーの能力の最大値を引き出す努力をする。
週刊連載をしていると作家も編集者もどうしてもツラくなる時がある。
作家が50点の出来でしか描けない時に、どうにかしてこれを70点の出来に近付けるのが大事だと思います。その為に編集者は何でもする。
もちろんそれ以上に、必ず作品が出続けるようにすることが大切だと思います。
―― 矢作さんもマンガの中身を作ったりしたことはありますか?
どの作品とは言えませんが、2年目くらいの頃ネームを1話丸々割って描いてもらったことがあります。
ずっと後になって、その作家さんには「マンガ家をナメてる」と怒られました(苦笑)。
僕もそう言われたら、そうだな。自分の領分ではなかったな。と。
でも、どんなことをしても編集者は作品をずっと出し続けることを請け負わないといけないと思います。
マンガを描く力がない編集者に出来るのは、何としても原稿を取るという努力(笑)。
―― 編集者にとって、一番良い仕事とはなんですか?
これは誰が読んでも面白いんじゃないか?と思える原稿を取れることですね。
しかも話の先行きがある程度見えているとなおいい。
そういう時は夜も良く眠れます(笑)
――では逆に、悪い時は?
やはり連載中の作品にダメを出した時です。世にいう「全ボツ」ですね。
そういう状況になる理由はさまざまですが、一番キツいのはキャラクターの作りに関わってくる時です。
キャラクターよりも話を優先して作ってしまったときに起こりやすいので、
もう一度キャラクターの根っこから話し合わないとならない。
―― 少し陳腐化した言い方になるかもしれませんが、
それが上手くいった時に「作品を良くすることに貢献できた」ということで、良い仕事なのかと
それはちょっと違うかもしれません。
一番良いのは、作家からで出て来たものそのものが面白くて、それが読者に伝わることだと思います。
だからそこに行くまでの打合せだとか、結果的にネームが一発OKにつながる準備が出来ていることが大切ですね。
とはいえ、漫画の作り方はそれぞれ。
作家によっては、とりあえず今週はどうやっても倒せないような強い敵を描いてしまって、あとは翌週考えよう。という作り方の人もいる。
それも一つの方法論です(笑)
色んな方法論があると思います。
繰り返しっぽくなりますが、編集者が作家の作品作りに介在しすぎることは、あまり良い事ではないと思っています。
ただ、連載というスケジュールの中ではなんとか作り上げて次の週に繋げる、ということもあるということです。
原稿は取る。そして、繋げた先が失敗だなぁと思ったら、さらに頑張って何とかしないとならない。
それが連載です。
インタビュー・ライティング:トキワ荘プロジェクト 菊池、番野
※本記事は、マンナビ「編集長の部屋」から特別掲載しています。
新人漫画家が、自分の「成長できる場」と出会うための漫画持ち込み・投稿・新人賞ポータルサイト“マンナビ”
“マンナビ”は、200近くのマンガ雑誌・媒体情報や100以上の新人賞情報が掲載された、新人漫画家・漫画家志望者向けのポータルサイトです。
出版社や新人賞の締め切り日など、あなたが知りたい情報で検索をかけて調べることも可能!編集者一人ひとりが情報を掲載する編集者情報など、ここでしか読めないコンテンツも充実した、プロ漫画家を目指す方必見のサイトです。
サイトはこちら→ https://mannavi.net/
Twitterはこちら→@mannavi_net